子どもが鉄道好きだと、鉄道関連の絵本を読むことも多いと思います。子どもと一緒に知識が増えていくと思うのですが、鉄道と言っても電車の車両だけでなく、色々な作業車両や鉄道を通す仕組みなども聞かれたりします。今まで鉄道に興味のなかった親にとっては、正直わからないことだらけです。ただ、絵本を読んでいると、子ども向けに罹れているので、そこまで知識がない親でも理解しやすいです。今回はそんな鉄道関連の知識は増えて、親にとってもわかりやすい絵本の紹介して、鉄道の色々な知識が増えるように絵本を紹介したいと思います✨

まずはノーマルな絵本からの紹介です☆
視覚デザイン研究所の絵本
一番電車関係の絵本で好きなのが、視覚デザイン研究所の絵本です。視覚デザイン研究所の絵本では、主人公のけんたが旅行などで電車に乗るお話です。こちらの本は、日本中のいろいろな電車が出てきたり、絵色々と細工がしてあるので、絵を細かく見てみると、大人も夢中になる絵本です。



この本の好きなところは、各ページの絵やコメントが詳細に描かれており、バムとケロの絵本シリーズのように、見るたびに「あ!こんなん描かれている!」という発見があり、とても面白いです。
しんかんせんでビューン
けんたがおじいちゃんおばあちゃん家がある秋田からけんたの家がある熊本まで一人で新幹線に乗って帰るお話です。大阪や京都の様子の絵が出てきて、高槻に住んでいるとなじみのある場所も見られるので、子どもたちもわくわくします。この本でおもしろいのが、
- 東京駅や大阪駅付近の様子の中で、けんたが乗っているメインの電車以外に、その場所を通過している電車が小さくたくさん書かれているので、「これ〇〇の電車だね~」など、話が広がって、車両の勉強になる
- 新幹線の路線図が表紙の裏に載っていて、わかりやすい
- 子どもが大好きなこまちとはやぶさが連結する瞬間が描かれていて、駅員さんが「やわやわ~」と連結時の合図が書いてあり、本当に「やわやわ」言っているのを実感でき、おもしろい
- 子どもが大好きなドクターイエローが出てくる
- 各ページに0系新幹線の顔がこそっと描かれていて、探すのがおもしろい
- 登場する新幹線が本の裏表紙に描かれていて、その新幹線たちがどこに出てくるのか探すおもしろさがある
- 鉄道以外にも、船や飛行機も描かれており、おもしろい
という感じです。



大阪や京都あたりの絵に、京都鉄道博物館や川崎の車両工場もあったね!
しんかんせんでゴーッ
こちらの本は、スイスから来たお友達のマーくんとけんたが一緒に九州から新幹線に乗って北海道のスポーツ大会に出場するお話です。この絵本でおもしろいのが、
- 立体的な日本地図に電車が走行している姿が描かれており、しかも駅名まで細かく書かれているので、親としてはこの場所にこんな感じの車両が走行しているのだなぁ~とわかりやすく、子どもにも説明しやすい
- 各ページにドクターイエローがこそっと描かれており、探すのがおもしろい
- 各ページに描かれている車両の名称などが下部に乗っているので、調べなくてもわかるのがありがたい
- 表紙の裏に鉄道博物館の日本地図があり、どこにどんな博物館があるのか見やすくわかりやすい
- 新幹線の製造工場の絵が描かれていて、新幹線の成り立ちがわかり勉強になる
- 新幹線の運転席の絵が描かれているので運転席の様子がわかる
- 種子島からロケットが飛んでいる姿が見られたり、スポーツ大会付近でブルーインパルスが飛んでいたりするので、電車以外の乗り物も見られて楽しい
- 日本地図にご当地のお弁当が描かれている
- 途中でお友達のマーくんが迷子になり、どこにいるのか探すのが楽しい



ドクターイエロー探すの楽しいね!
クリスマストレインしゅっぱつ
こちらの本は、ふと気づくとけんたが縮んで、けんたが遊びで作った模型の世界に入り込み、そこにいるこびと達と一緒にクリスマスプレゼントを組み立てながら、配っていくお話になります。
この本は上の2つの本とは違って、クリスマスをメインのお話にしているのですが、
- 実際に走行している車両が絵本に出てくる
- 各ページにサンタさんの絵が描かれており、探すのがおもしろい
- こびと達の発言がおもしろい
という感じです。クリスマスの時期になると、この本を取り出してきてよく読んでいます。



ここからはちょっとマニアックな絵本の紹介です☆
まよなかのせんろ
マルチプルタイタンパーってご存じですか?私はこの本を読むまで知らなかったのですが、真夜中に線路のゆがみを直してくれている車両になります。よく昼間に駅の端っこに停車していることもあります。


このマルチプルタイタンパーが真夜中に線路のゆがみを直す作業について、描かれている絵本になります。マルチプルタイタンパーは夜に作業するので、なかなか見る機会がないため、この本を読むと作業の様子がよくわかるので、おススメです。
じょうききかんしゃビーコロ
蒸気機関車ってたくさん種類がありますよね。D51、C62…私は蒸気機関車のこの形式を覚えるのがとても苦手だったのですが、こちらの本でなんとなくわかるようになってきました。
こちらの本はいつも機関区でほかの蒸気機関車を移動させるために引っ張っているビーコロ(B20)が他の蒸気機関車に憧れ、機関区の外を走る夢を実現させたお話になります。デゴイチくん(D51)やシロクニさん(C62)などが出てくるので、それでなんとなく形式を覚えることができました。
地下鉄のできるまで
こちらの本は、地下鉄ができるまでにどんな感じで工事されているのかということがわかる本になります。一度東京にある『科学技術館』というところで、地下鉄の工事をするゲームをしたことがあり、その経験もあったのでこちらの本で、色々な地下鉄の作り方や、地下鉄の形も何種類かあることも勉強になりました。



東京の科学技術館でやったゲームで見た絵だね!
ながいながいかもつれっしゃ
新幹線や在来線の車両の絵本は色々あるのですが、貨物の絵本ってあまり見ないですよね。こちらの絵本は貨物の事が書かれており、貨物の事をわかりやすく学べます。この絵本のおもしろさとしては、
- 貨物の車両は走る場所によって機関車が変わるので、どこらへんで何に代わるかわかっておもしろい
- コンテナを運搬する様子が見られておもしろい
- 運転席が見られておもしろい
- 貨物と一緒に走るサンライズが描かれていて、夜行列車を知ることができる
- コンテナの中身がどんな感じで積まれているのか、コンテナの扉がどう開いているのか知ることができる
- 絵をよく見ると、貨物で運ばれていた玉ねぎがお店へ運ばれていたり、引っ越しや宅配の絵が描かれていて、貨物が生活の身近な存在というのがわかる
- 急な上り坂では、コンテナを機関車が挟む形で走行しているのを知ることができる
- 貨物の一番長い走行距離、貨物列車と新幹線のの長さ比べ、走行しているときの運転士の交代時間など、色々な豆知識が書かれている
というところです。
貨物ってなかなか知る機会がないので、とても嬉しいです。ちなみに電車好きの夫がこの絵本を読んで子どもたちに知ってほしいポイントとしては、
- 桃太郎がコンテナを前と後ろで挟んで走行しているのは、広島にある「セノハチ」と呼ばれる場所で、後ろの桃太郎の車両は「押したろう」という可愛い名前で呼ばれている
- 東京貨物ターミナルは物凄く大きく、あまり全体を見渡せる場所はない。貨物は東京駅など都心を通らないのは、過去に都心を通っていたけれど、火災などの事故が色々起こったこともあり、都心あたりは通過せずに迂回するようになった
- 高槻は金沢経由で北海道へ行くレッドサンダーと東京へ行く東海道本線を走る桃太郎の2種類が見られるので、2種類が見られる高槻はとても貴重な場所
らしいです。



貨物が都心を通らなくなった事故の代表例が、下のような感じの事故です。その事故以外にも、ちょこちょこ事故があったようです。
でんしゃのつくりかた
電車を作る工場はなかなか見ることはできないので、こちらの本は電車ができるまでがよくわかり、おもしろいです。



細かいところは手作業でするようで、とても大変な作業ですね!
電車好きの夫がこの本を読んで子どもに知ってほしいポイントとしては、
- 東日本はJRが製作所を持っていて、新潟で車両を作っている
- 西日本はJRが製作所を持っていない
- 車両基地の見学はあっても、工場見学はなかなかなく、機密情報もあるので、工場内を絵本で見れて学べるのはすごい
- 絵本の中で新しくできた電車を引っ張っているEF64は、中央本線などの山岳地帯を走っていたが、それがブルーサンダーに代わり、西日本ではEF64は伯備線をよく通っている。EF64は高槻付近ではたまに見かけるが、廃車になるのは時間の問題なので、今のうちに高槻でEF64を見るのを堪能しておいた方がいい
だそうです。



以上、ここら辺あたりが鉄道関連で、親子で知識を楽しく増やせる絵本でした♡
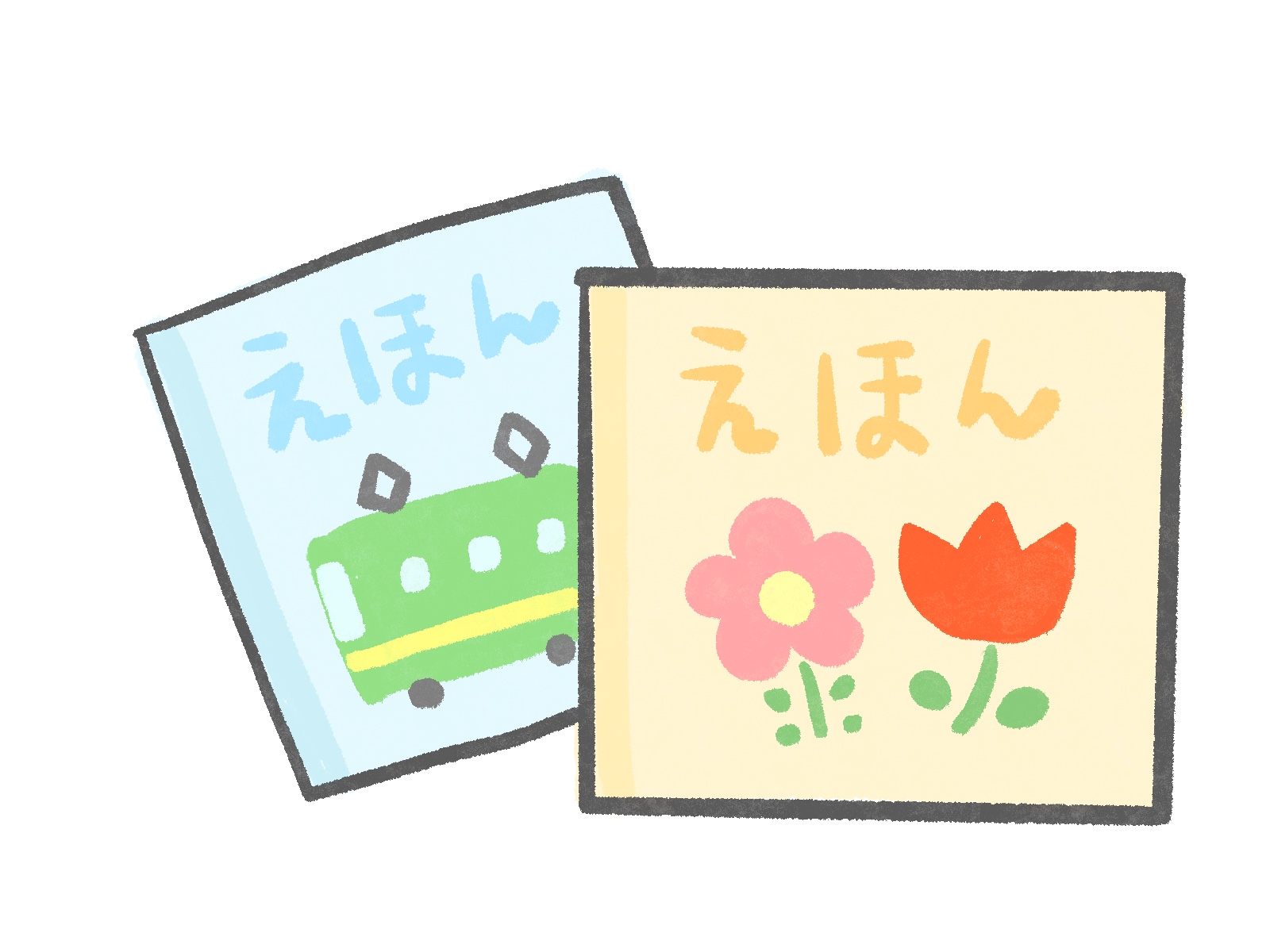

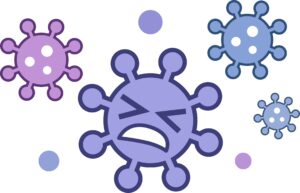






コメント